更新日2006/4/24
早春の能登ヘ 2006/3/11
冬にいけなかった遺跡めぐり。天気がいいとソワソワ。今日は能登に出かけよう!
目的は、杉谷ガメ塚。ガメ塚は竹林の中に埋もれているだろうか。
羽咋の柴垣まで行き、それから南下する。
途中、車窓から見える雑木林は、今年の大雪のせいか、倒木が目立つ。
林の手入れが、高齢化のために行き届かないということを目の当たりに見た気がした。
羽咋市の「柴垣ところ塚古墳」へ。
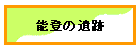 |
柴垣古墳群・ 柴垣ところ塚古墳 移築復元 |
羽咋市柴垣町本成寺内 |
「柴垣ところ塚古墳」は本成寺に移築保存されているという。まず、本成寺を探す。

本成寺本堂
応永3(1396)年妙成寺五世日立上人が、旧柴垣駅前付近に創建、
明治29(1896)年、時の住職日有上人が現地に移転新築した。
庭園は古色優雅な枯山水であり、特に大小数多くの庭石には、
地元産の滝石が配置されており独特の風情がある。
寺の収蔵庫には、裏山にある円山古墳からの出土品が整備保存されている。
本堂前に並んだ樽にはどんな意味があるのか、水がいっぱいの樽が並ぶ。
本成寺の墓地には円山1号墳の石棺が保存されている。
本成寺の境内に柴垣ところ塚古墳が復元されている。

柴垣ところ塚古墳全景
直径25m・高さ4mほどの円墳と推定されている。
柴垣ところ塚古墳は海岸に程近い平坦な段丘上にあった。
戦後の開墾に際して墳丘のほとんどを失い、石室下部石材が露出する状態に置かれていた。
1982(昭和57)年、圃場整備工事に先立ち、緊急発掘された。その後消滅。
羽咋市の旧歴史博物館の前庭に移築復元されたが、1994年、コスモアイルなどの建築の際、今の本成寺に移された。

T字型の横穴式石室
幅約0.79m・長さ1.6mの羨道部 奥行き1.74m・幅4.46mの玄室。
6世紀後半の築造
出土品は、須恵器・鉄鏃
このT字型石室は全国で50数例あるが、その内の8割くらいは九州・畿内に集中。
石川県では他に能登島の蝦夷穴古墳の石室があるが、板石を小口積みとしない点で異なる。
![]()
ところ塚の北西約150m地点に、柴垣ごぜん塚古墳があった。
これも著しく損壊。
石室の形は不明。(T字型の石室かもしれない)
出土品は、須恵器・石製紡錘車。
7世紀代の築造
![]()
柴垣古墳群データ

柴垣古墳群配置図
柴垣海岸には、標高20mくらいの海岸段丘が迫っていて
その丘陵上の先端部分に古墳が造られている
| 柴垣ところ塚 | 円墳 径25m・高さ4m |
T字形の横穴式石室 | 須恵器・鉄鏃 | 6世紀後半 | |
| 柴垣ごぜん塚 | 損壊 | T字形の横穴式石室か | 須恵器・紡錘車 | ||
| 柴垣観音山古墳 | 円墳 径43m・高さ4.5m |
二段築成 葺石あり | 円筒埴輪・朝顔形埴輪 | 6世紀初め | |
| 円 山 支 群 |
円山1号墳 | 円墳 径21.5m・高さ2.5m |
箱形石棺 | 人骨・甲・直刀・剣・刀子など | 5世紀中頃 |
| 円山2号墳 | 円墳 径8m | ||||
| 円山3号墳 | 円墳 | 箱形石棺か | |||
| 円山4号墳 | 円墳 | ||||
| 円山5号墳 | 組合式箱形石棺 | ||||
| 円山6号墳 | 円墳 | 横穴式石室 | |||
| 円山7号墳 | 横穴式石室 | ||||
| 円山8号墳 | 円墳 径10m | 横穴式石室 | |||
| 円山9号墳 | 横穴式石室 | ||||
| 円山10号墳 | |||||
| 柴垣親王塚 | 前方後円墳 全長35m |
葺石あり 横穴式石室 |
須恵器の甕・壺 | 6世紀中頃 | |
| 柴垣車塚 | 前方後円墳 | 現存しない | |||
![]()
柴垣の南、滝地区にも古墳群がある。(滝古墳群のページをご覧下さい)
遺跡地図では海のそばに、小さな前方後円墳のマークがあるので、見に行ったがわからなかった。
![]()
さらに南の柳田地区に、羽咋市の指定史跡である「山伏穴古墳」と「宮の山古墳」があるときき、探しに行く。
柳田の集落からゴルフ場に行く道を少し行ったところの右側にあるはずだけれど・・・・
道路わきに車を止め、わき道に入ってみたけれど、墓地しか見つからず・・・・
・・・・・・・あきらめた。
柳田の集落のほうから行けばわかるのか?
今度、もう一度よく調べて探してみよう
![]()
柳田台地の古墳 データ
羽咋市街地の北約3kmの柳田台地がある。
その台地上には、前方後円墳2基と大型円墳2基を含む10数基からなる古墳群がある。
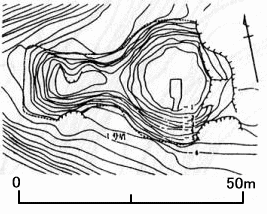
柳田山伏穴1号墳実測図(発掘調査された)
主軸をほぼ東西に置き前方部を西に向ける。
全長49mの前方後円墳。
後円部径29m・高さ7m 前方部幅18m・高さ8m
葺き石・埴輪なし
後円部南面に横穴式石室が開口する。
石室はすでに天井石を失っていた。
全長7.16m・玄室長さ4.42m・幅2.3mの片袖形、玄室床面には礫を敷きつめていた。
盗掘から逃れた副葬品は
管玉8・臼玉2・直刀片・刀子2・鉄鏃・心葉形杏葉・金具・須恵器など。
6世紀前葉ごろの築造
柳田山伏穴2号墳は長径17mの円墳
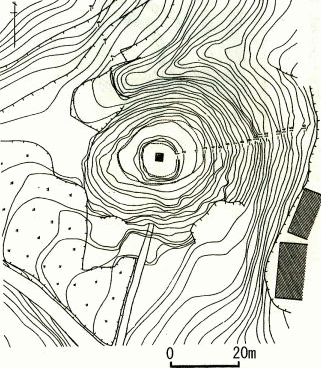
柳田宮の山古墳実測図
長径42mの円墳
三段築成
柳田うわの1号墳(径16mの円墳・横穴式石室・直刀や須恵器が出土)
柳田うわの2号墳(径13mの円墳)
柳田うわの3号墳(全長39mの前方後円墳)
柳田うわの4号墳(径8mの円墳)
柳田うわの5号墳(径10m以下の円墳)
柳田うわの6号墳(径25mの円墳)
この中で山伏穴1・2号墳と宮の山古墳が羽咋市指定史跡となる。
![]()
さあ、本日の目的地「杉谷ガメ塚」に行こう!
ガメ塚は雨の宮古墳群の南西、中能登町(旧鹿西町)金丸杉谷の集落の裏にあるらしい。
ガメ塚を探して山道を登っていったら、杉谷チャノバタケ遺跡に着いてしまった。
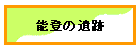 |
杉谷チャノバタケ遺跡 |
中能登町(旧鹿西町)杉谷 |

杉谷チャノバタケ遺跡全景
右側に水道施設がある。
その水道施設建設に先立ち発掘調査をしたら、
「日本最古のおにぎり」が発見された。
でも、現状はただの山!!
案内板から
| 鹿島郡中能登町(旧鹿西町)に所在。 眉丈山系から平野部に延びる丘陵から一部谷部にかけて(標高50〜110m)立地。 南北50〜100m、東西350m以上の広がりを持つ。 縄文時代から江戸時代の長期にわたる人々の様々な活動が確認された。 中でもチマキ状炭化米塊は「日本最古のおにぎり」として話題となった。 チマキ状の炭化米は、底辺約5cm、他の2辺が約8cmの二等辺三角形で、約3.5cmの厚みがある。 日本型のおくてのもち米を使用し、蒸された後二次的に焼かれたものと推定され、現在のちまきに近いものと考えられる。 チマキ状炭化米は、昭和62年11月、丘陵中腹に位置する第22号竪穴式建物の壁際から、単独かつ完全な形で出土した。 同建物は弥生時代の中期の終わり頃(1世紀前半頃)のもので、炭化米塊も同時期のものと推定される。 こうした調理・整形された米は、全国的にみても非常に少なく、なかでも本例は最古級のものだ。 機能的には携行・保存食だが、食用とは別に霊的なものへの供物あるいは厄除けという呪敵な用途をもっていた可能性がある。 |
![]()
チャノバタケから集落に戻り、ひなたぼっこをしているおばあちゃんに「ガメ塚」のことを聞いてみるけど、知らないと言う。
神社とお寺の場所を聞き、この辺りだと見当をつけてさがしたら、神社があった。
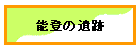 |
杉谷ガメ塚古墳 |
中能登町(旧鹿西町)杉谷 |
神社の背後、この鳥居の奥の竹林の中の左側にガメ塚は静かに眠っている。

杉谷八幡神社
産土神として昔から崇敬されてきた。
木曽義仲が小田中に陣をはった時に
戦勝を祈願したと伝えられている。
神社の本殿は鳥居の右側に小さなものがあるが、この本殿も円墳の上に建てられた?

杉谷ガメ塚 前方部から後円部を見る
前方部に比べ後円部がかなり高い。
竹林になっていて、昼でも暗く、大きすぎることもあって写真が撮れない。

後円部にあるくぼみ
盗掘坑か?
内部調査をしていないので、埋葬施設は不明。

ガメ塚実測図
全長約60mの前方後円墳
後円部径約37m(東西)・後円部高さ8m
後円部頂平坦面の直径約13m
前方部長約23.5m
前方部前端幅約29m
前方部高さ約4m
くびれ部幅約19m
葺石がある
段築はない
平野部から見える東側をていねいに造っている。
5世紀代の築造か。
ガメ塚は、杉谷A古墳群の主墳で、他に円墳13基・方墳8基が確認されている。
![]()
ガメ塚の西、金丸宮地地区には町指定史跡の「鳥屋塚古墳」があるらしい。
宮地地区で、歩いている女性に尋ねたけれどわからない。
ウロウロ探しまわったがわからずあきらめた。
よく調べてまた今度挑戦しよう!
鳥屋塚古墳(金丸宮地1号墳)は、円墳(径8m・高さ1.6m、両袖式の横穴式石室)。
現状は庭園・竹薮だという。町史跡。
次にかほく市の谷・亀田神社に向かう。
詳しくは、石川県加賀の遺跡の「谷・亀田神社古墳」をご覧ください
![]()
本日はここまで。
きちっと調べていったはずなのだけど、見つからない古墳。
見つかったときはとってもうれしい。
古代のロマンを探しに、またドライブに出かけるぞ。
![]()