| 加賀市・松山横穴古墳 |  |
北村さんちの遺跡めぐり
更新日2009/1/7
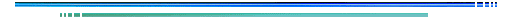
加賀市・松山横穴古墳
2008年10月25日の北陸中日新聞「散策ガイド」コーナーで
一向一揆の城があった松山城跡という記事が載っていた。
ここには松山横穴古墳があるという。
さっそく散策に行ってきた。
松山城跡は分校古墳群の南にある。
記事の通り歩いてきました。
 |
松山城址 |
加賀市松山町 |
松山町菅原神社近くの墓地に駐車し山を歩く
地元の人が整備した遊歩道と案内板がある。

松山城天守閣跡
松山城は1555(天文24)年、朝倉宗滴軍の加賀侵攻に際し、一揆方の砦のような役割をもった。
その後1567(永禄10)年、一揆方の拠点となったという記録がある。
その後、佐久間盛政の家臣の徳山則秀(五兵衛)が天正年間初期に改修・築城したと伝えられている。
松山城は、1600(慶長五)年、前田利長が大聖寺城攻めの本陣を置いたころまで使われていたと考えられている。

天守閣跡からの眺望
この場所からは、加賀平野が一望、小松市の矢田野町付近から大聖寺辺りまでを見通すことができ、
大聖寺城攻めの戦略を練るには絶好の場所だった。
(雑木がなければ・・・・)
松山城址の中に古墳がある。

古墳その1
古墳と書いた手製の案内板があるから古墳と分かる。
人間の目では古墳の高まりがわかるけれども写真ではわからない。

古墳その2
松山古墳群は5基確認されているという。
残念ながら、よくわからない写真ばかりで・・・・・・・・。

窯跡
遊歩道の最後の方に窯跡と書かれた案内板がある。
1848(嘉永元)年、藩窯松山窯が築かれたという。
山を下りたところ、竹内印刷という会社の道路を挟んで向かい側に横穴が・・・・。

松山横穴古墳全景
薄暗い山のふもとにある。
新聞に紹介されるまで、存在を知らなかった。

松山横穴古墳の中
天井が一部抜けているので中がよく見える。
岩を切り出した穴。
前庭部がある。
説明板がないので詳しいことは分からない。
![]()
30分ぐらいで松山城址の見学が終わってしまった。

松山古墳群周辺の地図
以前に分校チャカ山古墳群を見学。(分校古墳群のページ)
今回は松山城址のすぐ北にある分校カン山1号墳の見学に挑戦してみるが、
上り道が見つからず断念。
分校チャカ山古墳群・松山城址(松山古墳群)は地元の人たちが整備・保存をしているらしい。
毎年の草刈りなどは大変だと思いますが、がんばってください!
 |
吉崎御坊 |
加賀市塩屋町 |
石川県と福井県の県境の町吉崎で、蓮如上人は1471(文明3)年、道場吉崎御坊を築いた。
現在は、本堂跡を中心に当時をしのぶ遺跡があり室町中世の寺城の様子を残している。
蓮如上人はこの地に4年ほどしか滞在しなかったという。

吉崎御坊跡
現在は東西本願寺吉崎別院・吉崎寺・願慶寺となる。
資料館があるそうなので興味のある方はご覧下さい。
東西本願寺吉崎別院の住所は福井県あわら市吉崎となっている。
吉崎寺・願慶寺は石川県。
県境は通り1本。
![]()
吉崎御坊前の観光茶店で昼食。
小雨が降ってきた。なかなか雨がやまない。
 |
鹿島の森 |
加賀市塩屋町 |
吉崎御坊から北潟湖をへだてて目の前に浮かぶのが鹿島の森。
標高30m・周囲600m。

吉崎御坊から見た鹿島の森
もとは島だったのが、今は陸続きとなっている。
加賀では唯一の暖帯常緑樹林帯である。
子供たちが小さいころ、森の中に入り、アカデガニが歩いているのを見たことを思い出す。
数百年来、自然のままにしてある。
大事にしたい自然の風景だ。
 |
安宅関跡 |
小松市安宅町 |
初詣によく行く安宅の住吉さん。その住吉神社の後ろの松林の砂丘に安宅の関跡がある。

安宅関址の石碑が立つ
本当の安宅の関は海の中だという。
「義経記」を素材にした「勧進帳」の舞台である。

富樫・弁慶の像
歌舞伎「勧進帳」の終幕の段を
2代目市川左団次(富樫)、7代目松本幸四郎をモデルに製作されたものだそうだ。
「勧進帳ものがたり館」というのも最近出来た。
すぐそばの海は荒れている。
 |
石の木塚 |
白山市石立町 |
わが町白山市にも不思議な石造物がある。

石の木塚
石の木塚は5本の立石(流紋岩凝灰岩)からできていて、
最大の立石を中心にほぼ東西南北に配置されている。
石立町の町名の由来となる。
鎌倉時代にはすでに存在していたという記録がある。
古来から奇石として知られているが、立石の由来が伝えられていない。
(調べようとしたら祟りがあったともいわれる。)
浦島伝説もある。
弁慶にまつわる伝説もある。(?)
石の根は能登石動山に続くという伝説もある。

立石の基本平面図
(説明板より)
1993(平成5)年、中心石の南西を試掘調査をしたところ10C後半から11C前半の土器が出土した。
石を立ててから、40〜50cmの堆積があり、本来の中心石の高さは217cmあったとされている。
![]()
自宅発午前11時 自宅到着午後3時半
半日コースの遺跡めぐりでした。
![]()