�k�����̈�Ղ߂���
�X�V��2010/12/28
![]()
�M�c�_�{�ƈ�Ղ߂���
����2�B�e��2010/10/2�`3
![]()
���m������ڂł��B�@���H��A
AM�@7:35�@�L�R���̃z�e���G�A�[���C���@��
| ����ˌÕ� �u�i���Õ��Q |
�����s��R���u�i���������~ �B�e��2010/10/3 |
AM�@8:10�@����ˌÕ��@���B
�����(��ü�)�̂���ꏊ�͌Õ����B

����ˌÕ��E��~��
�삩��

����ˌÕ�
��~���̕����ɏ���Ђ����Ă��Ă���B

����ˌÕ�
���@�@ �O����(����)
�E���@��~��
����ˌÕ��́@�S��53m�̔����L���O����~��
�@��~���a39m�E����6.5m�@�O��������14m�E��21m�E����2.3m
2�i�z���ŁA���u���͂މ~�����֗�@��d�̎������������Ɠ`���
������͕̂s���B
6���I�̒z�����H

����ˌÕ��̎�����
������k�ɂ����Ă̓����̈ꕔ�Ƃ�����͂ގ��炪�c��B
�@�@�@�@�@
| �u�i����ˌÕ� �u�i���Õ��Q |
�����s��R���u�i������� �B�e��2010/10/3 |
AM�@8:24�@�u�i����ˌÕ��@���B
��v��r�̎��ӂɓ_�݂���Õ��Q�̒��ōő�K�͂̑O����~���B���1�����Ƃ��ď̂����B

�u�i����ˌÕ�
�E���@��~��
�����Ɂ@�Ⴂ�O����
�@

�u�i����ˌÕ�
��O���O�����B
�u�i����ˌÕ��́@�@�S��55m�̔����L�`�O����~��
�@�@�i�����������܂߂�ƑS��62m�j
��~���a40m�E����7m�@�O��������1.5m
�厲�͖k�������i�킸���ɖk���j
���u�ɂ͉~�����ցA�������ɉ͌��̕����߂���
��~���ɂ̓e���X�ʂ�����A��~�����猩���E�����тꕔ�ɑ��o������A���̏㕔�ɏ��֗�
�����͈�d�Ŕn���`
��̕���2��(�S�y�Ɩ؊�����)�m�F
�ܗ鋾�═��E�n��E����A����(�����`�E�{�`�E�W�`�E����`�E�~��)�⍂���ȂǑ������o�y�����B
1923�N�i�吳12�N�j
1982�N�i���a57�N�j�E1983�N�i���a58�N�j
2005�N�i����17�N�j2008�N�i����20�N�j�ƒ������s���Ă���B
| ����v��� �u�i�����Q |
���É��s��R���u�i������v�艺 �B�e��2010/10/2 |
��v��r�̎��ӂɓ_�݂����v��Õ��Q�̑O����~���B��v��1�����ƌĂ��ꍇ������B

����v���
�����Ȉē�������B
����v�����
����37.5m�̔����L�`�O����~��(�����������܂߂�ƑS��58m)
��~���a26.5m�Ɛ���
2�i�z���ł������Ƃ��l�����Ă���B�{�b���~�����ւ��o�y�B
�O�����ƌ�~���̋��ɕ��Ǝv�����Ɖ~�����ւ��m�F
��~���ɕ��u���͂މ~�����֗�̎c�����m�F

����v��Õ��̕��u
���u�̑������@������Ă���
2008�N�i����20�N�j�ɒ���
�@�@�@�@�@
| ����v��� �u�i�����Q |
���É��s��R���u�i������v�艺 �B�e��2010/10/3 |
��v��r�̎��ӂɓ_�݂����v��Õ��Q�̑O����~���B��v��2�����ƌĂ��ꍇ������B

����v�����
���u���핽����Ă��āA��������͍̂���0.5m���x
�ׂ��Ȍ`�͂͂����肵�Ȃ��B
2008�N�i����20�N�j�̔��@������
�@���C�n���ȓ��ł͍ŌË��i5���I�����j�̂��̂Ƃ����l�����ւ��o�y�����B
����v�����
�S��39m�̔����L�^�O����~��(�����������܂߂�ƑS����59m)
��~���a27m�@�u�i����ˌÕ��ƌ`�����Ă���B
���Ǝ�����O�炪�������ƍl�����Ă���B
�{�b��E�~�����ցE�n�^���ցE�{�^���ցE�l�����ւȂǂ��o�y
![]()
��v��r�̉���ɂȂ��Ă���Ƃ�����v��5�����͂悭�킩��Ȃ��B
���̕ӂ͂������܊J���̐^���Œ��B�V�������H��Z����ݒ��B
�����ɂȂ�\�������炵�����E�E�E�E�E�E���̂��Ƃ��낤�B
| �����ˌÕ� ���w��j�� �u�i���Õ��Q |
�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |
AM�@918�@�����ˌÕ��@���B
�L���ȌÕ��������w�ɂ͌����Ȃ������E�E�E

�����ˌÕ�
��~���̒��㕔�̕��ɔ����g���Ă������Ƃ���
�����˂ƌĂ��悤�ɂȂ����ƌ����Ă���B
���݂͔��͂قƂ�nj����Ȃ��B
�����ˌÕ����@�S�� 115m�̎苾�^�O����~��
�@�O�������� 43m�E�O�������� 6.7m�i�k���j/ 5m�i�쑤�j�E�O������ 40m
�@���тꕔ�� 25m
�@��~���a 75m�E��~������ 15.2m�i�k���j/ 12.6m�i�쑤�j
���тȌ`�����Ă��邪��������Ȃ̂��͂悭�킩��Ȃ��B
�O����2�i�A��~��3�i�z��
�O�����[�Ɩk���A��~���̊e1�����ȏ�ɑ���o�����������\��������B
���ւȂ�
��̕���2��̉\��������B
�{�b��E���W�E�͂����E�P�E�y�t��ЂȂǂ��o�y
4���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B
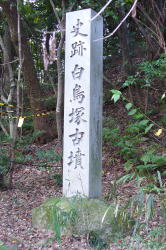
�G�ɕ����Ă��āA���u�ɂ͂Ȃ��Ȃ����荞�߂Ȃ��̂ŁA
�Δ�̎ʐ^�ł��B
��~�����͂ւ���ł���Ƃ������E�E�E�E�E�B
�܂����������āE�E�E�E�B
�@�@�@�@
| ����1���� �s�w��j�� �u�i�����Q |
�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |

���H�����Ɉē��B

1�����̎�O�ɓ�̐Αg��
���H����オ���Ă����̂Ƃ���
�Ђ���Ƃ���8�����̂��́H

����1�������u
�����Õ��Q�̒��ł́A��������`���قڊ��S�Ɏc�����Ύ�������
����1�������@�@�@�a17.5m�i�����j16.5m�i��k�j�E����3.5m�̉~��
�������Ύ��͕��ʓ����^�E�������őS��9.8m�Ő����ɊJ�����Ă���B
������4.2m�E�ő啝1.6m�E����2.4m�@�A������3.2m
6���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B
�吳����̒����œy���ȋʁA�S�V���o�y�����Ƃ̋L�^������B
���a36�N�i1961�N�j�̒����œy��═��o�y
����18�N����19�N�i2006�N?2007�N�j�͈̔͊m�F�����ŁA
�@C�^�ŊJ�����œr�ꂽ���a(��4.9m)���m�F�A
���a���܂߂�1�����̋K�͓͂���25m�E��k��24.5m�B
������3�E���q��2�E�S�V3�E�n��ꎮ�E�{�b��E�y�t��ЂȂǂ��o�y�B
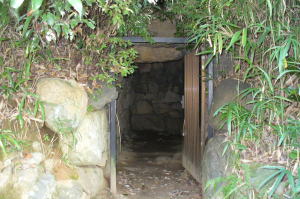
����1�����Ύ��J����
�@�����ɊJ�����Ă���
���͂������ĂȂ������B

����1�����Ύ�����
���������K���ɐς�ł���悤�Ɍ�����B

����1�����Ύ���������O������B
���ǂ͐����ɂ��ꂢ�ɐς܂�Ă���B
| 1���� | �a17.5m�i�����j16.5m�i��k�j�E����3.5m�̉~�� |
| 2���� | �a12m�̉~���Ő������ɊJ�������������Ύ�������B ���a36�N�̒�����ɊJ���ɂ���ď����B ���r���o�y |
| 3���� | 2�����Ɠ��K�͂̉~�� �J���ɂ����2�����Ɠ������ɖŎ� |
| 4���� | 17.0m�~16.4m�̉~�� ���쐼�ɊJ�������������̉������Ύ�������B �y�t��E�{�b��E���q1�E�S�V2�E�D�֓���o1�@ |
| 5���� | �a10m�E����2.5m�̉~���B �V��Ǝv����ނ��I�o�B�������B |
| 6���� | ���Ƃ̒��ɂ���ˏ�Ɏc��B �Õ��Ɛ��肳��Ă��邪�������B |
| 7���� | �a��10m�̉~���B4�����������ɔ��� �\�y������{�b��̚��W�����S�Ȍ`�ŏo�y �쑤�ɊJ�����Ă����Ύ��̐����ǂ��c�����m�F�B ������A���������B |
| 8���� | �~���B����18�N����19�N��1���������ŁA�אڂ���ʒu��8�����̎������B ���u�̐��y�Ǝ������n�\���Ɏc�����鎖���m�F�B 6���I�㔼�ɒz�����ꂽ�\���B �{�b�킪�o�y�i�B |
�@�@�@�@
![]()
���J�R�R���̌Õ������w�ɍs���B���J�R�R���֍s�����͗�������֎~�̕W�����ڂɂ��B
�����܂ŗ����̂Ɉ����Ԃ��Ȃ��Ƌ��s�˔j�B
����̒��ԏ�ɂ�20�䂭�炢���Ԃ��Ă���B
���w�������͔����ː_�Ђ̐��|�̓��ŁA��w���炵���l��������������B�@
AM�@10:00�@�@�����ː_�В��ԏ�@��
| �e�[�u���X�g�[�� ���J3���� �u�i�����Q |
�����s��R���u�i�������J �B�e��2010/10/3 |
�����ː_�Ђ̒��ԏꉡ�ɕs�v�c�ȋ����E�E�E�E�B

�e�[�u���X�g�[��
���J�R3�����̐Ύ�
�S��5m�قǂ̉������Ύ�
���J�R3�����́@���J�R���k���̒i�u��ɘ[�ɂ���������Õ��ŁA�Ύ��̏㔼�����I�o���A
�傫�ȓV����e�[�u���̂悤�Ɍ��������Ƃ���n���ł̓e�[�u���X�g�[���Ƃ����Ă����B
��n�J���ŏ��ł̂��߁A�R���̔����ː_�В��ԏꂻ�ɐΎ����ڒz���ꂽ�B
�{�����̏��ցE�e��ʗށE������S������ށE�{�b��Ȃǂ��o�y
6���I�̑O���̒z���Ɛ��肳��Ă���B
�A�����Ė������s��ꂽ�ƍl������B
���J�R�̐����ɂ͎R������[�ɂ�����40�����Õ����������B
�啔����6���I�`7���I�̂����ł��ׂĉ~�����B�@�@�@�@(��������)
| �����ː_�ЌÕ� �u�i���Õ��Q |
���É��s��R��厚�u�i�������J �B�e��2010/10/3 |
���J�R�̎R���ɂ�������ː_�Ёi�����ݼެ�j�́A�Õ��̏�Ɍ����Ă���B

�����ː_�ЌÕ�
���a30m�̉~���B
���Ă͑S��50m�̑O��������Ƃ��O����~���Ƃ̐������������A
�@����20�N�i2008�N�j�̏������ʼn~���ƒf�肳�ꂽ�B
2�i�z���@������@���ւȂ�
���a�����Гa�������@����A�傫�Ȑɓ˂����������Ɠ`�����邱�Ƃ���A
�@�G�����Ύ��ƍl�����Ă���B
4���I�㔼�̒z���Ɛ��肳��Ă���B
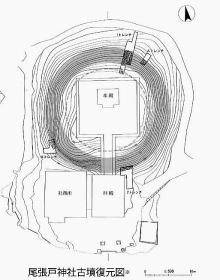
�W��198.3m�ߓ��J�R�̎R���ɂ���B
2009�N�̔��@�����ŁA�a27.5m�̉~���Ɗm�F���ꂽ�B
4���I�O���̒z���Ɛ��肳��Ă���B
�Ήp�����̏�ɂ܂���Ă����ƍl�����Ă���B
(����31/3/9�@���˂̌Õ��U�v���w�������)
�Õ��̖k���ɂ͑O�����̂悤�Ȓn�`�̕���������B
�O����~���ƌ��ԈႦ���̂͂��̂��߂Ȃ̂��Ǝv���Ȃ��猩�w�����B

�����ː_��
���Ă͔M�c�_�{�Ɏ�����Ђł������Ƃ����B
�������_�i�̂��ɓ��J���_�j�̕ʖ��������A���J�R�i�����R�j�̖��O�̗R���Ƃ��Ȃ����B
�u�a�����̐_�Ƃ��Ēm����B
���Ђɂ͒��ЁE��Ђ̓�Ђ�����A
�@���Ђɂ͔��R�e���Q���A��Ђɂ̓C�U�i�M�E�C�U�i�~���J���Ă���B
| ���ЌÕ� �u�i���Õ��Q |
���É��s��R��厚�u�i�������J �B�e��2010/10/3 |
���J�R�R��������120m���炢�̂Ƃ���ɂ���B

���ЌÕ���~��
�����ɒ��Ђ�����B
���ЌÕ��́@�@��~�����R��(�k)�Ɍ�����
�S��63.5m�̑O����~���@(�O������`�̊�d�̏�ɉ~�����悹������ȕ��`)
��~��3�i�@�O����2�i�z��
��~�����̔�����傫���@�荞��ł����Ă���B
�Ζʂɕ���(�͌���)����@�~�����֗��͂��߂���B
�]�ˎ���̋L�^�ɂ����Ώ����ς݂̒G�����Ύ����瓺���i�̏o�y�̋L�^������B
�����ː_�ЌÕ��ɑ���4���I������̒z���Ɛ�������Ă���B
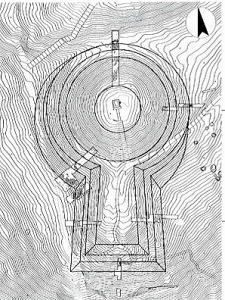

���ЌÕ��O����
2009�N�̒����ŌÕ��̉~�����̒��_��������
���a30�`40cm�E������70cm�̉~�����ւ�5�{����Ԃŏo�y�����B
(���ߖ߂����Ƃ���)
���ЌÕ����炳��ɓ�ɂ�������ЌÕ�������B(���w���Ȃ�����)
��ЌÕ������a30m�E����2m�̉~��
�@���Ȃ��@������
�@���n���琄�肷���5���I��̒z�����H
| ���������Q | �@�B�e��2010/10/3 |
�������Õ��Q�́A�����R�̓�Ζʂ̐������珯����̉͊ݒi�u��ɂ���B
6���I���`7���I������5���̌Õ����m�F�B�@3������5�����������B
| 2���� | ���u�͂قƂ�Ǘ��� �쐼�����ɊJ�����鉡�����Ύ����I�o �{�b��i�����A���A��r�A��t�����j�Ƌ����o�y |
| 3���� | ���� ���a�������Ȃ����a��15���̉~�� ������ɊJ�������������Ύ� �{�b��i�����r�j�A�y�t�킪�o�y �Ύ�������R���q(���q����)�������o�y |
| 4���� | ���u�͂قƂ�Ǘ����@�Õ��̋K�͕͂s�� �Ύ�������͐{�b��i���g�A���W�A�����j�A���A�S���A�S�V���o�y |
| 5���� |
�@�@�@
������5����
�������Õ��Q�t����s�ʖ쒬�˖{
�B�e��2010/10/3
AM�@1055�@������5�����@��
5�����̕��u�́A�啔�����J���ɂ���Ď����A���łɉ������Ύ����I�o�B

������5����
���Ǒ�����
�L���_�n�̒��ɑ傫�Ȑ��I�o�B
�V��͂Ȃ��B
������5�����̉������Ύ���
�@��������ɊJ������S��8.05 ���̋[�������^�Ύ�
�����͓����ŁA����4.72 ���E�ő啝2.2��
����ɂ͗����ƍ����z�����B
�A���͒���3.3 ���E�ő啝1.4 ��
�J�����Ɍ������Ă��J���B
�{�b��A���A�品�A���q�A�S�V�A�n��A�S���A�u���o�y�B
�╨�̏o�y���畡����̒Ǒ����s��ꂽ�ƍl������B
���a54�N����

������5����
����������

������5����
�Ύ��̂܂��ɂ͐��U�����Ă���
�Õ��ɂ��Ă̐����͂Ȃ����A�_���Ȃ��̂ƍl�����Ă���炵���A
�u�䏊�����_�v��u�ʐ��_�v�Ə����ꂽ�Δ肪�����Ă���B
�Δ�͐Ύ��̐ނō���Ă���̂��H
�@�@�@�@�@
������3����
���������Q�t����s��������
�B�e��2010/10/3
AM�@1130�@������3�����@��
�Z��̑���ɌÕ����������݂����Ȋ����ŕۑ�����Ă���B
�Z��Ɉ͂܂�Ă���̂ŁA�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B

������3�����@�k�����H����
�����ɂ��~���I
������3�����́@�@���a15���̉~��
���a�Ȃ�
�������Ύ��͑S��6.7m�A�ő啝1.5m�B
���a47(1972)�N�ɒ����A��r�A�L�����_���o�y
����(���q����)�Ɋh�����Ă���Ύ�������R���q�������o�y�B
���a49(1974)�N�����ۑ��B

������3�����@�쑤����
������ɊJ�������������Ύ�
�@�@�@

������3�����@�Ύ������
�@�@

������3�����@�@�Ύ�����
�@�@�@�@
| �C��7���� �C���Õ��Q ����ݸ�� |
�t����s�C�������R�{ �B�e��2010/10/3 |
AM�@1140�@�R�{�����@�C��7�����@��
����19�N�ɒ����A�����̈�p�Ɍ��n�ۑ����ꂽ�B

�C��7����
�W��43���[�g���̒i�u���ӂɈʒu����B
����͂��̎��a���Ύ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
��������������Ȃ��B
�C����7�����́A�C���Õ��Q�ł͗B�ꌻ������@�a12m�E����2.4m�̉~��
������@���a����
�����ɊJ�������������Ύ�������(���ߖ߂���Ă���)
�{�b��̚��W��1�E�y�t��Ђ��o�y
����19�N����
| �V���R�Õ� | �t����s�嗯�� �B�e��2010/10/3 |
���u�̎��͂�����������v�悪�i�s���ł���B

�V���R��
��������B
���Ă͕��u��ɏ����ȎЂ��u����Ă����B
�V���R�Õ��͏�����̎��R��h��i�W��32m�j�Ɉʒu����@�a28m�E����4.5m�̉~��
������@�Õ������͒�������핽
��̕��͖��m�F
�ԍʂ��{������d������A�����A��䓙���o�y
4���I��̒z���Ɛ��肳��Ă���B
2004(����16)�E2007(����19)�N����
| �e���ˌÕ� | �t����s�嗯�� �B�e��2010/10/3 |
AM�@1155�@�e���ˌÕ��@���B
�_���Ћ����E�q�a�̐����ɂ���B

�e���ˌÕ�
���O�͏@�ǐe�����邢�͌�ǐe����
�@��i�������Ƃ̓`���ɂ��B
1968�N�i���a44�N�j���@�����A
�@�t����s�̌Õ��ŏ��߂ĕ����ۑ����ꂽ�B
�e���ˌÕ��́@�a15m�E����3.5�`4m�̉~��
������@���K�͂Ȏ��a����
���Ɍ������ĊJ�������������Ύ��͑S��5.1m�@����������4m
�@���͉��ǂ�1.3m�A���������ł�1.6m�A����1.8m
�@���ǂ͎�������ς݂ŁA�V��Ƃ��Ē���1.5�`1.6m�E��1m�̐�5���g�p
�@�����̏��ʂɂ͑�l�̎�̂Ђ���̉͌���~���B
�����̈ꕔ�═��A�{�b��E�o�^�y��E����3�Ȃǂ��o�y�B
6���I���`7���I�����̒z���Ɛ��肳��Ă���B
�o�y���������Ȃǂ���푒�҂�2�l�Ɛ��肳��Ă���B
���u����͒����̎R���q���̔j�ЂȂǂ��o�y�B

�e���ˌÕ��Ύ�����

�e���ˌÕ��Ύ�����
�ߏ��ɂ��ޒj�����ʂ肩����A�������b�������B
�e���ˌÕ��̐����ɂ���������n���̕��ŁA�����̍ۂɂ͒��쌧�̑厺�Õ��Q�ȂǂɎ��@�ɍs�����������B
�@�ǐe���̕�Ƃ���ɂ́A�N�オ����Ȃ��ˁ[�Ƃ����b�������B
![]()
���R�Ɍ������r���A�K�X�g�t����≺�X�ɂĒ��H�B
| �ˌÕ� ���j�� |
���m�����R�s�� �B�e��2010/10/3 |
PM�@1:20�@�ˌÕ��@��

�ˌÕ��j�Ռ����ē��}�@(��������)
�W��31m�̑�n�̒[�ɒz����A
�Õ��̐����ɂ͖ؑ]��ɂ��`�����ꂽ���삪�L����B
���u��\�ʏ�ɖ�50cm�̐��y���Ȃ���A���c�����̎p���Č����ꂽ�B

�ˌÕ�
�k������
��O�ɂ͈ꕔ��������������Ă���B
�ˌÕ��́@�S��123m�̑O����~��
���m�����̌Õ��ł͒f�v�R�Õ��Ɏ�����2�Ԗڂ̋K��
�@��~���a78m�E����12m�@���тꕔ��43m�E����5.5m
�@�O��������45m�E��62m�E����7m
�O����2�i�E��~��3�i�z���@������
�e�i�̃e���X�ɂ͚�^���ւ�����
�O�����̕����ɂ͒Ⴂ�d�����肱�̒d���͂ނ悤�ɉ~�����ցE�h�t����`���ւ�����
�Õ��̎��͎͂��R�̒n�`�𗘗p������@��̎���������B
���̎�������Õ������̂��тꕔ���O�Ɍ������ĐL�т闤��������B
4���I������̒z���Ɛ��肳��Ă���B
�˂̂ق����P�R�E���˂ȂǂƂ��Ă�Ă���

���u�ɕ��ׂ�ꂽ�@�Ԃ���^����
������~��

�o�y�������ւ̓W��
�������̃K�C�_���X�{��
�@�@�@�@
| ���R�_�ЌÕ� | ���R�s�H�����싽 �B�e��2010/10/3 |
PM�@2:07�@���R�_�ЌÕ��@���B
�ˌÕ��̃K�C�_���X�{�݂̓W���Ŕ��R�_�ЌÕ��Ƃ����̂��������̂ŁA
�@���R�_�Ђ�T���Č��ɍs�����A���u���킩��Ȃ��E�E�E�E�E�E�E

���R�_��

���R�_�ЁE�Гa
�Гa���Õ��̏�Ɍ��Ă��Ă��邻���ȁB
�@�@�@
| ���c�R���É��ʉ@ | ���R�s�厚���R �B�e��2010/10/3 |
��t�����c�s�̐��c�R�V�����̕ʉ@������B

���R���c�R�ƌĂ�Ă���B
���a28�N��{�R����s�������̂����g���������J�n���ꂽ�B
���C�O�\�Z�s���������Ԃ̎D���ƂȂ��Ă���B
| ���V�{�� ���j�� |
���R�s�厚���R���k���R�� �B�e��2010/10/3 |
PM�@2:28�@���V�{���@���B
���c�R���É��ʉ@�̐�������R��o��ƒ��ԏꂪ����A�������班��������Ƃ���ɕ��u�B
���R���R(�C��136m)�̒���ɂ���B

���V�{�Õ��O�����쑤
�Õ��̖��̗̂R���Ƃ��Ȃ��Ă���u���V�{�_�Ёv�����B
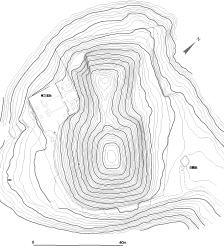
���V�{�������}
(�w�j�Փ��V�{�Õ���P�������T�v�x����)
�S��72m�̑O�������
�������48�~49m�E����8m�@�O������43m�E����6m
�O������k���̉L�����ʂɌ�����
�S�ʂɕ�����@���ւȂ��@�����Ȃ�
���a48�N���@����
�������ɂ����G�����Ύ��́A����4.8m��0.96m�œ����̕ǑS�ʂɃx���K�����h���Ă����B
�Ύ������Ɋ��|�`�؊����u����Ă����ƍl�����Ă���B
�ΐ��i7(��3�E�L�`��1�E�ԗ�1�E���q2) �@�ʗ�140(�Ő�������3�E�d�ʐ��Nj�137)
��11�ʁi�O�p���_�b��4�E�Ή���������_��b��1�E���i�K��l�_�`��1�E�l�b�`��1�E�l���b����4�j
�S���i�i�S��4�E�S��9�E�S���S��17�E�S�V6�E�Z���`�S��3�E�L�ܓS��3�E�j��1�EY���`�S��2�E�����K���i���j
�Ȃǂ��o�y
�Ύ��k���ɂ͊p�I��z�������Ύ�������B

���V�{��
�G�����Ύ���
7���̝G���ȔΏ�̓V��ɂ���ĕ����Ă��āA
���̏������F�S�y�ŕ����Ă����Ƃ����B

�Õ��֍s���r���ɐ��H�Ղ�����B
�V���n�̓d�Ԃ��ȑO�ʂ��Ă����B
�ȂA�₵���Ȃ��B
���V�{�Õ��͕W��143���̔��R���R���ɂ���A�k���ɂ͖ؑ]�������Ŋ��e�����s�L���̌Õ��Q������B
(�L���̌Õ��ɂ��Ă��E����2���������������B)
| �������Õ� | ���R�s�厚���R �B�e��2010/10/3 |
PM�@3:10�@���������@��

�������Õ��͖������̋����ɂ���B
�Õ��͌����̔w��ɂ���

���̌����̍����̕�n������@���u�O�����ɏオ��B
�Ⴊ���킭�Ă������茩�w���ł��Ȃ��B
���@�����͍s���Ă��Ȃ��B

�������Õ����ʐ}�@�w�j�Փ��V�{�Õ��������x����
�S��95m�̑O����~��
�@��~���a52m�E����7.5m
�@�O������50m�E����43m�E����5.5m
�i�z�����݂���\��������B
���͂ɂ͏��`�̎����ƊO�炪���݂��Ă������Ƃ������ł���B
�O��̖k�����́A���S���R���ɂ��傫���j��Ă���B

��������
�O���������~��������
��~�����ɂ͂��Č��������݂����悤�ŁA�L�����R�ɂȂ��Ă���B

��������
��~������O����������
�O������ɂ͈�א_�Ђ�����B
�O�����͖����������̕�n�ɂȂ�A���ς��Ă���B
�@�@�@�@
![]()
�\�肵�Ă������m���̌��w���I�����B
�����������Ԃ�����̂ŁA�̌Õ��̌��w�̎��A�����Ă��܂�����͗Y�_�Ђɍs���A�ʐ^�̎B�蒼���B
![]()
PM�@4:10�@��͗Y�_�Џo��
PM�@4:25�@�e����IC
�@�@�@�@�@�@�@��{JCT
�@�@�@�@�@�@�@��JCT
PM�@5:25�@�˃��xSA�ɂċ����Ƌx�e
�@�@�@�@�@�@�@����PA��O5km�����肩�玖�̂̂��ߏa��
�@�@�@�@�@�@�@15�����炢�ŏa��E�o
PM�@6:20�@���SA���X�g�����ŗ[�H
�@�@�@�@�A��̍��������͂�������1000�~
PM�@8:10�@�A��@�@
����̗��́@���s����630km�������B
�M�c�_�{�Q�q�ƈ�Ղ߂���@�@�����
![]()